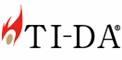”うちな~”文化って!?


文化という響きにはちょっと近寄りがたいイメージがあるけど、ちょこっとお付き合いの程を。祝日以外その筋の人に任せておけばいいや、と何となく避けてしまう”文化”。特に沖縄の場合特殊な地域性、歴史的な背景から素晴らしい文化になっているにも関わらず地元の人間でさえよく分からない。まあ、生活そのものが文化なのだから改めて語る必要がないと言えばそれまでだが―。どちらかと言えば本土からの移住者の方がキチッと押さえている場合が多い。そこで身近なところから沖縄文化の入門編的なことを書いてみよう。素材は”音楽、食、言葉”。
まずは”音楽”。昨今は沖縄ブームと言われる位、三線などを取り入れた沖縄音楽が巷にあふれている。じゃあ”沖縄音階”は知ってる?何を隠そう僕自身以前からギターなどで音楽には関わってきたがそんなに前から知ってた訳じゃない。「ドレミファソラシド」から二つの音が抜けたのが沖縄音階。さてどの音が抜ける?眼を閉じて口ずさんでみよう・・・そうです抜けるのはレとラ、「ドミファソシド」です。近くにピアノなど楽器がある人はレとラを抜いて適当に弾いて見て。「お~、オキナワ~!」ってなるハズだよ。
次に”食”。それを知るには庶民の食堂に行くのが一番いい。メニューに”~ちゃんぷるー”なるものが多い。ちなみに”おかず””野菜いため”は”~ちゃんぷるー”と同義語。これらには必ず〈植物性タンパク=豆腐〉〈動物性タンパク=ポーク又は肉類〉〈ビタミン=野菜〉の三要素が入る。時期によって野菜の種類、あるいはその比率が違うから〈ゴーヤーちゃんぷるー〉〈マーミナー(もやし)ちゃんぷるー〉〈豆腐ちゃんぷるー〉などとなる。”野菜いため”や”おかず”はウチナ~ンチュの手抜きの性格からきた「え~い、めんどくさい!」って付けた名称だ。そうそう僕が内地に行って食堂で”野菜いため”なるメニューを見つけ喜んで注文したら、何とそれは野菜だけの炒め物。思わずクレームを言おうかと思ったが・・言ってたら多分逆ギレされてただろうな、ハハ。ところで沖縄は暑い気候と、その昔冷蔵庫なる文明の利器がなかったせいで食材に”旬”というのは求めず、野菜なども量を炒めて調理するのがほとんどで、そのビタミンの減少を植物、動物性タンパクで補ったバランス料理がチャンプルーだ。生野菜をサラダなどに使うのは近年になってからじゃないかな。
最後に”言葉”。これこそ文化と言われる位多岐にわたるから、ここではさわりの”ボイン”、何だかヤラしく聞こえるから、入門編の”母音”を取り上げよう。母音操作だけで標準語を沖縄的にすることも出来る。沖縄の母音はこれも又”あいうえお”から二音抜ける。というよりここでは二音変化すると言った方がいいか。”え”が”い”に、”お”が”う”に吸収され”あいういう”となる。たとえば〈心(こころ)=くくる〉〈想い=うむい〉〈手=てぃ〉〈目=みー〉・・。民謡のカラオケで字幕をよく見るとスモール”ぃ””ぅ”が多く使われていることが分かる。例を琉歌の”ちんさぐの花”でみてみよう。
ちんさぐぬ花や ちみさちに染(す)みてぃ (ホウセンカの花は 爪先に染めて)
親(うや)ぬゆしぐとぅや 肝(ちむ)に染(す)みてぃ (親の言うことは 心に染めて)
関連記事